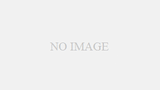問題 <R4年午前問19>
送電用変圧器の中性点接地方式に関する記述として、誤っているものは
<解答の選択肢>
- 非接地方式は、中性点を接地しない方式で、異常電圧が発生しやすい
- 直接接地方式は、中性点を導線で接地する方式で、地絡電流が大きい
- 抵抗接地方式は、地絡故障時、通信線に対する電磁誘導障害が直接接地方式と比較して大きい
- 消弧リアクトル接地方式は、中性点を送電線路の対地静電容量と並列共振するようなリアクトルで接地する方式である
【出典:令和4年度第一種電気工事士筆記試験-午前問19】
誤っているのは、3「抵抗接地方式は、地絡故障時、通信線に対する電磁誘導障害が直接接地方式と比較して大きい」
同じ年度問題
・前の問題(問18)
・次の問題(問20)
・令和4年度-午前問題
解法と解説
方針
送電線路の接地は 13年で 5回出題。合格必須事項をマスター後の習得を。
ふくラボ流攻略法
電路の中性点の接地方式は
- 一次送電線路:直接接地
- 二次・三次送電線路:抵抗 or 消弧リアクトル接地
- 配電線路:非接地
一次送電線路は、地絡事故時に地絡継電器を確実に動作させるために、地絡電流が最も大きくなる直接接地方式を適用している。つまり、抵抗接地方式は、直接接地方式より地絡電流が小さい。
一方、通信線などの微弱電流線への電磁誘導障害の大小は、電流の大小に一致する。
これから、誤っているのは選択肢3「抵抗接地方式は、地絡故障時、通信線に対する電磁誘導障害が直接接地方式と比較して大きい」と判断する。
まとめ
送電線路の接地は 14年で 5回出題。合格必須事項をマスター後に、早めの習得を。
電路の中性点の接地方式は
- 一次送電線路:直接接地
- 二次・三次送電線路:抵抗 or 消弧リアクトル接地
- 配電線路:非接地
類似問題・関連記事
・R4年午前-問19(接地方式)
・R2年問19(配電用変電所)
・H30年問19(接地方式)
・H23年問18(接地方式)
・H21年問19(送電線総合)
・変電設備の解説
同じ年度問題
・前の問題(問18)
・次の問題(問20)
・令和4年度-午前問題