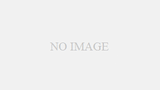問題 <R4年午前問21>
高圧母線に取り付けられた、通電中の変流器の二次側回路に接続されている電流計を取り外す場合の手順として、適切なものは
<解答の選択肢>
- 変流器の二次側端子の一方を接地した後、電流計を取り外す
- 電流計を取り外した後、変流器の二次側を短絡する
- 変流器の二次側を短絡した後、電流計を取り外す
- 電流計を取り外した後、変流器の二次側端子の一方を接地する
【出典:令和4年度第一種電気工事士筆記試験-午前問21】
変流器二次側に接続された電流計を取り外す手順は、3「変流器の二次側を短絡した後、電流計を取り外す」
同じ年度問題
・前の問題(問20)
・次の問題(問22)
・令和4年度-午前問題
解法と解説
方針
CT二次側の機器の取外しは、試験対策とともに、あなたが電気工事士として活躍するときに役立つ知識。覚えておいて損はない。
ふくラボ流攻略法
電流が流れた状態の変流器 CT の二次側を開放することは厳禁。
CTは、原理は変圧器(トランス)と同じだが、決定的に違う点は、CT一次側の電流値の大小に応じて二次側に電流を発生させる点。
この点をもっと別の言葉で言い換えると、一次側に電流が流れているときは、二次側回路に力ずく(?)でも電流を流そうとする。
このため、二次側回路の抵抗が低いときには問題ないのだが、抵抗が高いときに問題が発生する。なんせ力ずくで電流を流そうとするのだから、抵抗が高いのなんておかまいなし。とびっきりの高電圧を発生させてでも電流そうとする。
他の記事を参照すると、数千ボルトもの電圧を発生させれるらしい…
だから、CT 一次側に電流が流れているときに二次側を開放=高高抵抗状態にしてしまうと、二次側に高電圧を発生させる。これ、非常に危険。
したがって、CT 一次側に電流が流れている状態で、二次側回路の電流計を取り換えるなどの接続を変えたいときには、
- 二次側端子両端を短絡させ、端子間電圧 ~0V を確認
- 機器を取り外す、交換する
- 短絡(回路)を外す
の手順を厳守すること。
まとめ
CTで押さえるポイントは次の3つ。
- 単線図・複線図と接続
- 機能と仕様
- 二次側回路の取外し
類似問題・関連記事
・R4年午前-問21(CT二次側機器の取外し)
・R3年午後-問48(CTの複線図)
・R2年問23(CTの用途)
・R2年問48(CTの接続台数)
・H30年問45(CTの働き)
・H29年問20(CT二次側機器の取外し)
・H29年問46(CTの接続)
・H28年問23(SRの用途; CTで引掛け)
・H28年問50(CTの接続台数)
・H27年問46(CTの複線図)
・H25年問22(CTの外観と働き)
・H23年問44(CTの端子)
・H22年問46(CTの働き)
・H21年問20(CT二次側機器の取外し)
同じ年度問題
・前の問題(問20)
・次の問題(問22)
・令和4年度-午前問題